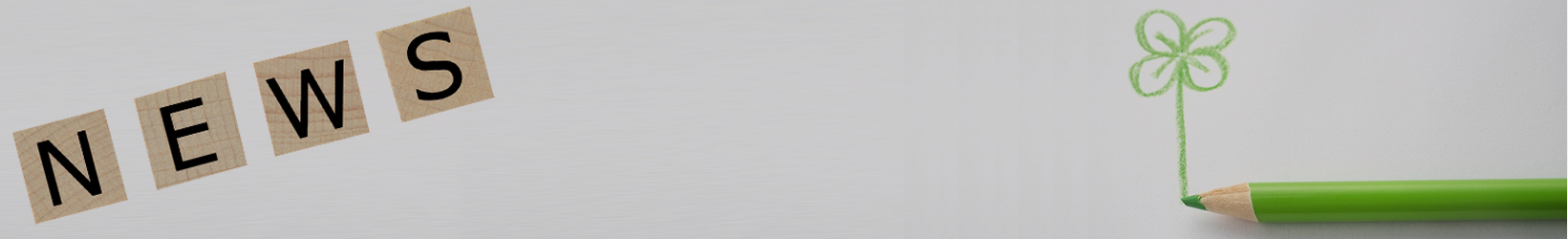減価償却方法としての「定額法」と「定率法」の違い
減価償却は、企業や個人事業主が事業のために取得した資産の取得価額を耐用期間にわたって費用として配分する会計上の手続きです。その計算方法として、日本の税務上よく用いられるのが「定額法」と「定率法」の2種類です。これらの違いを理解することは、適切な会計業務や税務申告を行う上で非常に重要です。
まず、定額法は、資産の取得価額を耐用年数で均等に割り、その金額を毎年同じ額ずつ減価償却していく方法です。たとえば、取得価額が1,000万円で耐用年数が20年の資産であれば、定額法償却率は0.05(20分の1)となり、毎年50万円を償却します。定額法では、取得価額という変わらない基準額に対して毎年同じ償却額を計上するため、資産の帳簿価額(未償却残高)が減っていっても、償却額は変わらないという特徴があります。
一方、定率法は、毎年の帳簿価額、つまりその年時点での未償却残高に一定の割合(定率法償却率)を掛けて償却額を算出する方法です。初年度の償却額は高額になりますが、償却が進むにつれて帳簿価額が減少するため、毎年の償却額も次第に小さくなります。つまり、定率法では資産の価値が早い段階で大きく減少すると考え、使用初期の負担を重く、後年は軽くする計算方法です。
両者の決定的な違いは、基準となる金額にあります。定額法は毎年「取得価額」に対して一定率を掛けるのに対し、定率法は「帳簿価額」に対して一定率を掛けます。したがって、定額法では償却額が一定ですが、定率法では年を追うごとに償却額が減少していきます。定額法は計算が容易で予算管理もしやすいという利点があり、定率法は定額法に比べ投資初期に多額の減価償却費が計上されるため、初年度の税負担を軽減でき、資金繰りにおいても利点があるといえます。
減価償却方法の選択は、税法や企業の会計方針に基づき決定されます。なお、法人税法では資産の種類によって認められる減価償却方法が異なる場合があるため、税法に沿った正しい処理が求められます。